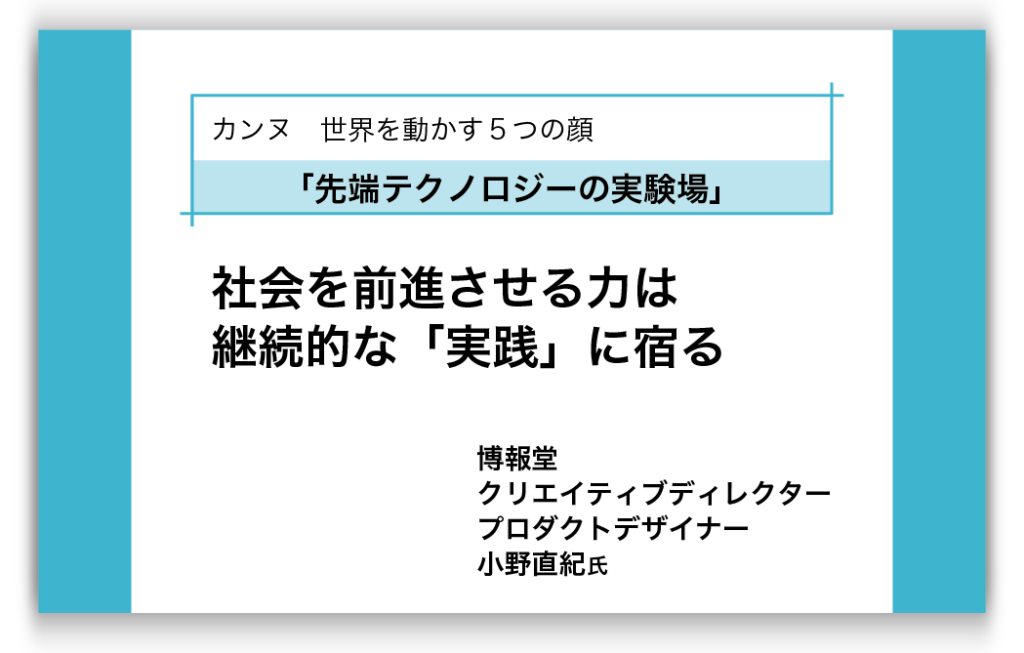
2021年のカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル(以下カンヌライオンズ)を、“テクノロジー”という視点で見ると、もはやそれは特別なものではなかった。ほとんどの部門の受賞作に何らかのテクノロジーが使われていたのだ。
11年にカンヌライオンズが「広告の祭典」から「クリエイティビティの祭典」になってちょうど10年。テクノロジーはあらゆる領域のエグゼキューションの手段として、当たり前の選択肢となっていた。

小野 直紀
(おの なおき)
2008年博報堂に入社後、空間デザイナー、コピーライターを経てプロダクト開発に特化したクリエイティブチーム「monom(モノム)」を設立。社外では家具や照明、インテリアのデザインを行うデザインスタジオ「YOY(ヨイ)」を主宰。15年より武蔵野美術大学非常勤講師。19年より博報堂が発行する雑誌『広告』の編集長を務める。
リアルな場に“事件”を起こすテクノロジー
僕が初めてカンヌに訪れたのは2010年、最後の「広告の祭典」の年だった。博報堂に入社して3年目。このとき目撃した受賞作は、今でもよく覚えている。当時、テクノロジーにまつわる受賞作を見ることができたのは、主にサイバー部門とチタニウム部門の2つだけだった。
この年のカンヌライオンズで、特に印象に残っているのは、サイバー部門のグランプリを獲ったNikeの「Livestrong」だ。舞台はツール・ド・フランス。インターネットを通して、がん患者やがんで亡くなった人へのメッセージを募集し、3万6000ものメッセージを自転車レースが行われる道路上に、ヘリからの映像で視認できるサイズで印字した。これを実現するために開発されたのが、巨大な文字を道路上に印字するためのマシン「Chalk Bot」だった。

サイバー部門が創設されたのは1998年。そこから12年経っており、とんちの効いたバナー広告、Flashを駆使したリッチなウェブサイトなど、画面の中での表現が一通り出切った頃だったように思う。
だからこそ、リアルな場に起こしたこの“事件”は衝撃的だった。「Chalk Bot」で使われているテクノロジーは決して最先端なものではなかった。しかし、この試みは新しかった。既存の入手可能なテクノロジーを活用して、リアルな場に事件を起こす。それがテレビやインターネットを通して広く届けられる。そんな手法があるのかと胸を躍らせた。
この年のサイバー部門のもう1つのグランプリも、同様の手法だった。フォルクスワーゲンによる「The Fun Theory」だ。「走る喜びと環境配慮の両立」を目指す技術を広めるキャンペーンで、「楽しさが人々の行動を変える」という考え方の下、様々な機器を開発し実証実験を行った。例えば、エスカレーターではなく階段の利用率を上げるために開発した、踏むと音が鳴る鍵盤のような階段。ゴミのポイ捨てを減らすために開発した、ゴミを捨てるとそのゴミがはるか下まで落ちていくような効果音が出るゴミ箱。こうした実証実験を通して「やるべき」を「やりたい」に変えるアイデアの可能性を提示した。

これもまさにリアルな場に事件を起こすものだと言える。使われているテクノロジーは平凡だが、それによって生まれたメッセージは心に突き刺さるものだった。
コミュニケーションとプロダクトの間
12年、初めてのカンヌライオンズとは全く異なる衝撃が走った。サイバー部門とチタニウムでグランプリを受賞した「Nike+ FuelBand」によってだ。
「Nike+ FuelBand」は、日常生活における消費カロリーや歩数などの活動量を測定・記録するリストバンド型デバイスだ。今ではFitbitやApple Watchなど、よくある製品カテゴリーではあるが、当時は非常に新鮮だった。

そしてそれは、アスリートだけではなく、一般の生活者がナイキを身に着ける動機をつくる目的で開発されたプロダクトであり、広告だった。「生活すべてが、スポーツだ」と、メッセージに合わせてかっこいい映像をつくるのが従来の広告だとすれば、「Nike+ FuelBand」はこのメッセージを実世界に体現したプロダクトと言える。それを身に着けることで、運動する人が増える。そしてナイキ製品が売れる。コミュニケーションとプロダクトの間にある、新しい何かが生まれたように感じた。
「Nike+ FuelBand」は、07年にサイバー部門のグランプリとチタニウムライオンを獲った「Nike+」の延長線上にある。
「Nike+」は、ランニングシューズにスマートフォンと連動するセンサーを取り付け、走行時間や移動距離、走行ルートなどが記録されるランニング管理システムだ。SNS機能もあり、ランナー同士が競争したり、メッセージを送り合ったりできる。このシステムを利用した大規模なランニングイベントを実施するなど、ランニング体験をより豊かにするためのプラットフォームとして展開されていた。
「Nike+」も「Nike+ FuelBand」も手掛けたのはR/GAだった。ナイキというスポーツウェアブランドが、テクノロジーを使ったプロダクトやサービスをつくったという驚きと、その裏側に広告クリエイティブエージェンシーがいたという二重の驚きがあった。
この驚きをきっかけに、僕自身の興味はテクノロジーを活用したプロダクト開発へと移っていった。
プロダクト開発の実践と苦悩
14年、「Nike+ FuelBand」は残念ながら事業を閉じることになる。しかし同年、カンヌライオンズにプロダクトデザイン部門が新設された。「Nike+ FuelBand」以降、広告業界にプロダクト開発の機運が高まっていたことが影響したのだろう。
その頃の僕は、個人でプロダクトデザインの活動をしながら、博報堂ではコピーライターとして広告制作に携わっていた。プロダクトデザインと広告制作。この2つの職能を生かして、世の中にまだないプロダクトをつくれるのではないか。そんな思いから僕は社内の有志とともに博報堂の中にプロダクト開発に特化したクリエイティブチームを立ち上げた。それがmonom(モノム)だ。
その後、ぬいぐるみをおしゃべりにするボタン型スピーカー「Pechat」を開発、博報堂初のハードウェア販売事業を立ち上げた。また、博報堂グループのSIXが開発する「Lyric speaker」のプロダクトデザインや、ユカイ工学が開発するしっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」のクリエイティブディレクションに携わった。現在は、17年にプロトタイプを発表したウェアラブル英会話教師「ELI」の事業化に向けた開発を進めている。

これらの実践による学びは大きかった。商品のアイデアを出したり、開発したりすることはある程度できる。そのためのノウハウやネットワークも構築できた。しかし、それを事業として成立させ、価値を提供し続けることの難しさは、やってみてはじめて理解したのだ。
表現における“新規性”が価値となる広告の世界であれば、テクノロジーの実験的な活用で成立するかもしれない。しかしプロダクトやサービスの世界では、それだけでは意味がない。広告制作のゴールが“点”であれば、プロダクトやサービス開発のゴールは“線”。事業会社にとっては当たり前のことを、痛切に思い知らされた。
新規性よりも継続的なコミットメント
ときは流れ2018年。プロダクトデザイン部門審査員をしないかと声がかかった。「Nike+ FuelBand」の衝撃から6年。広告の世界でどんなプロダクトが生まれているのか。また、自分がmonomでやっていることはどう位置づけられるのか。このことを確認したいという思いから審査員を引き受けた。
プロダクトデザイン部門には、エージェンシー、メーカー、スタートアップなどから、多種多様な作品が応募されていた。大きく分けると以下の3つだ。①メッセージを伝えるためのアイテム。②新しい機能や体験を生み出しているプロダクト。③社会を実際的に変革しているプロダクト。monomがやっているのは②と③だ。
審査においては、販売や継続的提供、規模感など、生活や社会の変革に実質的にコミットしているかどうか、 そのポテンシャルがあるかどうかを重視した。
この年、グランプリを受賞したのは、「KINGO」だった。コロンビアの低所得世帯向けの電力不足を解決するためのプリペイド方式の太陽光発電システムだ。小型の太陽光パネルとバッテリーを地域の雑貨店などに無償で提供し、住民は発電された電力を1時間単位で購入することができるというものだった。
特別新しいテクノロジーが使われているわけではないが、テクノロジーと仕組みを組み合わせて、この地域の人たちの生活にコミットしている点が評価された。

この年のイノベーション部門でも近い志のものが受賞していた。「My Line」だ。My Lineは、インターネットへのアクセスができないコロンビアの人たちのためのプロジェクトだ。Googleアシスタントをインターネットではなく、旧式の携帯電話でも利用できるようにすることで、音声によって情報を届けられるシステムを構築した。

これもテクノロジーとしては全く新しくない。旧式の携帯電話とGoogleアシスタントという既存のテクノロジーを組み合わせて課題解決を図っている。テクノロジーやアイデアそのものよりも、コロンビアにおける情報格差を解決しようという志と実際的なコミットメントが評価されたのだろう。
1回限りでその効力を失う“新規性”に価値を置くのではなく、社会を前進させるための継続的なコミットメントを価値とする。それは広告業界におけるクリエイティブの弱点でもあり、伸びしろでもある。monomでの活動も踏まえ、そんなことを感じたカンヌライオンズだった。
テクノロジー視点で見る2021年のカンヌ
冒頭でも書いたように、21年のカンヌライオンズはあらゆる領域でテクノロジーが当たり前のように使われていた。その中でも目を引いたのは、やはり社会を前進させるために、継続的なコミットメントを志しているものだった。いくつか例を示す。
デザイン部門でグランプリを受賞した「NOTPLA」。イギリスのNotpla社がプラスチックゴミの削減を目的に、海藻や植物由来の成分を使った“消える容器”「Ooho」を開発。飲料やソースなどのゴミの出ない容器として活用され、6週間で自然に分解され、そのまま食べることもできるものだ。13年にプロトタイプが発表されて以降、事業化への準備を進めていた。今後、容量20~150mlのOoho製造装置を事業者にリースし、材料のカートリッジを販売するビジネスモデルを展開していく計画だそうだ。

ラジオ&オーディオ部門とファーマ部門でグランプリを獲得した「Sick Beats」。嚢胞性線維症に苦しむ子どもたちのための特別な振動ベスト。通常のベストは空気圧によって胸を強制的に振動させるもので、心地のいいものではなかった。そこで、ウェアラブルデバイスブランドのWoojer社は、40Hzの音波振動を与える治療法に着目。Spotifyと連携し、40Hzの周波数の曲に合わせて振動するベスト「Sick Beats」を開発。「治療」と「音楽」を融合した点が秀逸だ。

SDGs部門でグランプリを受賞した「The 2030 Calculator」。スウェーデンのフィンテック企業Doconomy社は、商品のCO2排出量を簡単に計算できるツール「The 2030 Calculator」を開発。商品のカテゴリー、商品の総重量、各パーツで使用する素材の重さ、サプライヤーや工場、流通センター間の距離、輸送に用いる交通機関、製造に使用するエネルギー源などを入力すると、その商品のCO2排出量を計算できる。これまで多くのコストと時間がかかっていたCO2排出量の計算が、潤沢な資金のない中小企業でも無料で簡単にでき、ブランドの透明性を高めることができるようになった。企業側の環境負荷軽減への態度表明は生活者のそれを促すきっかけにもなる。世の中全体の環境に対する意識改革に貢献するツールだと言える。

今回の文章は「カンヌにおける先端テクノロジーの実験場」というテーマだった。最初にこのテーマを見たとき、2つの違和感を覚えた。果たしてテクノロジーの「先端性」は重要なのか。そして、我々は「実験」をしているのだろうか。
ここまで書いてきて、改めて実感した。新しい何かを生み出すのに、テクノロジーの「先端性」は必須ではない。そして、社会を前進させるクリエイティビティは、1回限りの「実験」ではなく、継続的な「実践」に宿る、ということを。
