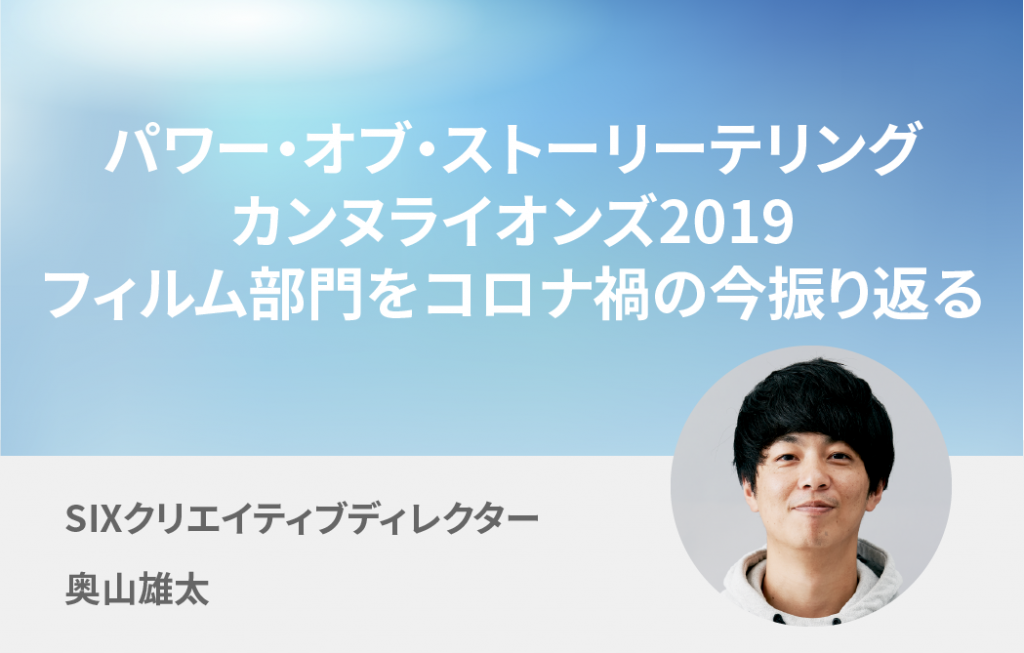
1985年東京生まれ。東京大学経済学部卒業。博報堂入社後、2017年よりSIXに所属。CMプランナーとして育った知見と技術をアップデートし、映像のストーリーデザインやコミュニケーションのストーリーデザインに取り組む。国内外で11のグランプリを含む100以上のアワードを受賞。
筆者は、2019年6月に開催されたカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル(以下カンヌライオンズ)2019に、フィルム部門の審査員として参加した。〝2020〟ではなく、〝2019〟である。本来であれば、今年の6月にもカンヌライオンズが開催され、今頃、世界中の圧倒的なアウトプットを見て、尊敬し、嫉妬し、議論していたことだろう。しかし、コロナの感染拡大を受けて、広告の世界大会であるカンヌライオンズ2020は、オリンピック同様、来年へと延期になった。
広告は「時代を映す鏡」と言われる。時代が変われば広告も変わる。特に、同時代の人間やブランドを描くフィルムやCMは顕著だ。そうした意味で、歴史的にも類を見ない形で世界のあり方や価値観が変わった20年の今、1年以上前のカンヌライオンズについてレポートすることに若干の違和感があるかもしれない。その意味で、これからの時代においても通用するフィルムの力とはなにかを、少し意識しながら振り返りたいと思う。
ブランドアクションとしてのフィルム
昨今の広告業界で最も語られるキーワード「パーパス」。様々な解釈があるが、筆者の認識では〈ブランドの社会的な〝存在意義〟を示し、世の中と価値観を共有すること〉。ジェンダー、障がい、地球環境、人種差別、貧困格差など、社会課題に対する意思や姿勢、行動を示すことによって、ブランドへの共感をつくるケースが増えている。フィルム部門もこの大きな潮流の中にあり、その文脈で高い評価を獲得し金賞を受賞したのが、Libresse(イギリスの生理用品ブランド)の“VIVA LA VULVA”。貝殻、折り紙、財布、フルーツ、ファッション、アニメーションなど多種多様なモチーフが、女性器の形を模しながら、Fatboy Slimの名曲「Praise You」を歌うという型破りなミュージックビデオである。グランプリ投票まで残ったキラキラの金賞だ。
Libresseの調査によれば、44%の女性が自分の女性器に自信がないという。これまでタブー視されていた女性器というテーマに踏みこみ、肩の力の抜けたユーモアのある軽妙な世界観でその多様性を称えることで、劣等感や恥を感じずに女性器について語ることができるオープンな文化をつくっていくというコミュニケーション。タブーについて語る勇気と、美しいビジュアルインパクトと、圧倒的なフィルムクラフト。〝語られる〟武器を備えてバイラル・ミュージックビデオとして波及していくことで、議論を生み出しオープンにしていく。Libresseの公式リリースを読むと、“fights against the myths, insecurities and stereotypes that women are subjected to when it comes to their genitals”(女性器にまつわる神話や不安、固定観念と戦う)と書いてある。ブランドの持つ社会問題への強い意志が、フィルムの力と出会って、すばらしい形で「アクション」に定着している。
ブランドが社会課題に向き合っていくとき、そのメッセージをフィルムで語ったりすると、「口だけでなく行動で示せ」と思われてしまう節がある。具体的なアクションのほうが説得力があるからだ(映像において、感情はセリフより行動で描けと言われることに少し似ている気がする)。このバイラル・フィルムは、「メッセージ」でなく「アクション」である。このテーマについて語ること自体が勇気ある「アクション」であり、ユーモアフルな語り口も勇気ある「アクション」である。そして「語ること」は、フィルムという伝統芸能が最も得意な領域である。ここに、パーパス時代におけるフィルムのあり方の1つのヒントがあるのではないだろうか。
トリックスターとしてのアジア
アジアからの出品で最も善戦していたのは、銀賞を受賞したKPLUSの“FACE/OFF”。KPLUSはタイのモバイルバンキング・アプリで、そのメジャーアップデートを訴求するオモシロCM。整形大国とも呼ばれるタイの整形事情を背景に、恋人の女性が変幻自在に顔(というか全身)を変えながら、変化のすばらしさを男性の悲哀とともにユーモアフルに描くもの。WHAT TO SAY(訴求点)をどれだけ飛距離をもって面白く伝えられるか、という古典的な話法である。
唯一のアジア人審査員として悔しく感じたのは、アジアからの出品に対して評価基準がどこか歪んでいるということ。ほかの作品については、論理と感性の両輪で繊細に解像度高く議論されていたものが、アジアの受賞作については「クレイジーで最高だ!」といった解像度という言葉と程遠い直感的な意見が多い。振り返ってみれば、日本の過去のフィルム部門受賞作は、予想外すぎるクレイジーな笑いや、異常なまでに凝ったクラフトの作品が多いかもしれない。それは私たちの1つの武器であるし、1つのアイデンティティとして大事にしていくべきだが、どうメインストリームで世界と戦っていくのかも考えていかねばならない。
ストーリーテリングとしてのフィルム
最後に紹介するのは、グランプリを受賞したニューヨーク・タイムズの“The Truth Is Worth It”。ニューヨーク・タイムズは数年前から“Truth” をキーワードにコミュニケーションを展開しており、フェイクニュースが問題視され、報道機関が否定的に見られる時代の中で、「真実」の価値とそれを追求するブランドの姿勢を世界に示そうとしている。
今回の“The Truth Is Worth It” は、ドナルド・トランプ大統領の不正な税対策から、不法移民の子供たちの真実、ニューヨーク地下鉄の組織的劣化の原因まで、ニューヨーク・タイムズの実際の記事が生まれるまでの取材の軌跡を追体験させる映像である。映像の主役は、カタカタカタとタイプされていくシンプルなテキスト。テキストの内容、レイアウト、タイミングと、背景映像や環境音との組み合わせとによって、ジャーナリストが真実を追いかけていく過程にある、汗、葛藤、緊張、試行錯誤、忍耐、恐怖、勇気、決意の物語を雄弁に語っていく。筆者もこの映像を初めて見たとき、「これだけ最小限の要素で、ここまで強くブランドや感情を語れるのか」と衝撃を受けたものだ。ほぼ圧勝のグランプリだった。ブランドの存在意義と態度を身体的にグッとこさせる話法のアイデアと、それを完璧に定着した精緻なエグゼキューション。この時代のフィルムのあり方を象徴する素晴らしい仕事である。
ここには日本人にとって、あるいは、コロナショックのただ中にある20年の私たちにとって、希望があると思う。この映像には、破格の予算の世界的なセレブも音楽もCGもない。そこにあるのは、ブランドの強い意志と行動、そしてそれに真摯に向き合い、想像するだに途方に暮れるようなテキストの構成を練り上げ、ストーリーテリングへと昇華した作り手たちの汗である。
「大作の時代は終わり」──そんな声が広告業界のあちこちで聞こえてくる。ソーシャルディスタンスを考慮した撮影編集環境の変化。コロナショック不況による予算の圧縮。斬新なアイデアに大きな予算を投じ、大規模な撮影と労働集約型のプロダクションワークによってブランドを演出することは難しくなってきている。今、私たちにできることは、ストーリーテリングという広告フィルムの原点に返り、世界の心を動かすブランドの真実と人間の物語はなにかを、真摯に探し続け、考え続け、行動し続けることなのかもしれない。真実を追いかけるニューヨーク・タイムズのジャーナリストのように。
