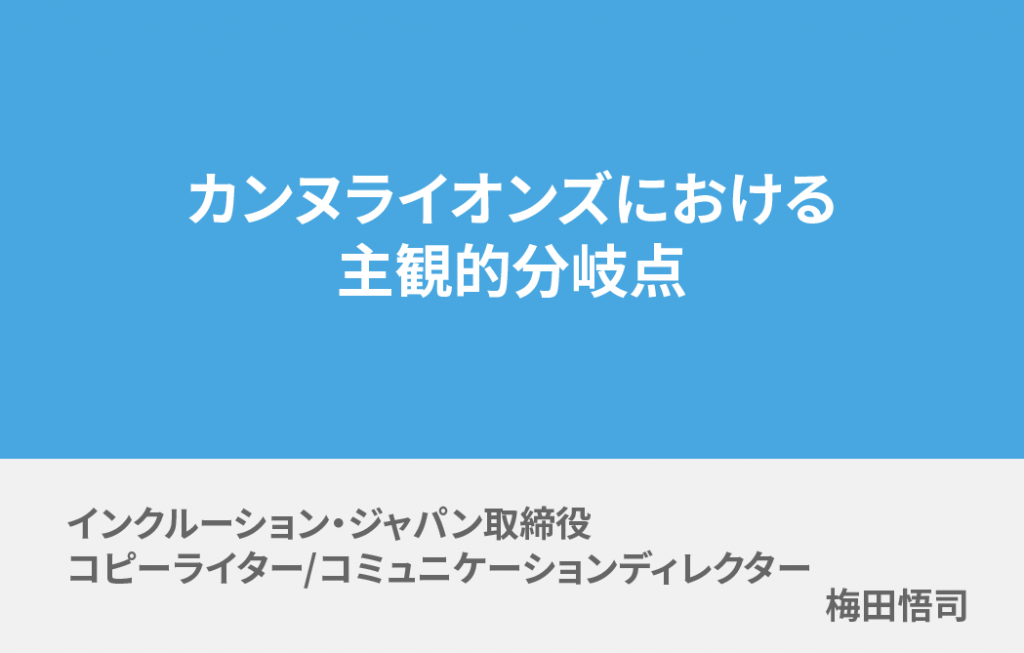
ソーシャル・グッドへの分岐点
2020年6月後半に予定されていたカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル(以下カンヌライオンズ)2020は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止となった。この時期の風物詩とも言える、受賞事例の速報や解説などが流れてくることもなく、物寂しい気もする。本連載でも、カンヌライオンズ2020におけるSDGsに関する傾向について解説する予定だったのだが、本稿ではいままでの流れを振り返ることとしたい。
時を同じくして、カンヌライオンズ日本事務局を務める日本経済新聞社は、設立から10年が経過する同PR部門受賞作を無料公開する「Cannes PRLions 10 YEAR EXHIBITION IN JAPAN」を開設しているので、併せてご覧いただきたい。
私が広告会社に入社したのは04年である。広告動向に無知であった私は、広告制作の手法を学習する対象として、広告賞という存在に出合うことになる。学習方法としては、受賞広告を表現手法ごとに類型化していく中で、型を知るというものである。当時はまだ、商品特性をいかに誇張して表現するかの大袈裟競争という意味が強く、その方向性が「インパクトを持たせる」「別のもので例える」「ストーリーを紡ぐ」といった手法に紐づいていた。
こうした大袈裟競争に変化が見られたのは、10年初頭である。「ソーシャル・グッド」の文脈が生まれたのだ。具体的には、12年にカンヌライオンズで新カテゴリー「Grand Prix for Good」が創設され、クリエイティブ・ブティックであるドロガー5の手掛ける「Help: I want to save a life」が初代のグランプリ作品となった。本プロジェクトは、絆創膏の箱に血液検査キットを同梱することで、骨髄バンクへの登録の入り口を作り出すものである。
本広告をきっかけに、多くのクリエイターが「自分たちが持っているクリエイティブの力を社会のために用いることができる」という刺激を受けることになった。クリエイター層の意識を社会課題に向かせたという点において、本事例は大きな分岐点になったと言っても過言ではないだろう。
▶Help: I want to save a life
乱立期から、洗練期へ
その12年、私はカンヌライオンズの会場におり、講演や授賞式などにはほぼ参加せず、会場に置いてあるパソコンでひたすら応募広告のケースビデオを見ていた。当時は「Grand Prix for Good」が新設されたタイミングということもあり、NPOやNGOを中心に数多くの社会的活動がエントリーされていた。その一方で民間企業はと言うと、知らない企業や商品も多いため、その背景を十分に理解できていない可能性もあるが、「なぜこの企業や商品がこの活動を行うのか」という文脈が見えないものが数多く存在していた。いま思えば、ソーシャル・グッドの過渡期だったのだろう。
それ以降、社会的活動に取り組む主体にも変化が見られるようになった。NPOやNGOの活動に関連する応募が主流だったが、徐々に、民間企業が主体となる社会的活動が目立つようになっていったのである。言葉を変えれば、クリエイターがNPOやNGO活動に協力するという段階から、普段から携わっているクライアント案件で、企業と共に社会的活動を生み出そうとする視点が生まれた、と理解することができよう。
そこで、名実共に広告と社会問題との関係性を前進させる分岐点になったのが、15年のPR部門でグランプリを受賞した、P&Gの「Like a Girl」であろう。このキャンペーンはP&Gの生理用品Alwaysの広告で、「少女のようにふるまって」と言われると、かわいく、ぶりっ子のような振る舞いをしてしまうという、アンコンシャス・バイアス(無意識な思い込み)の存在を明らかにするものである。企業やブランドへの落とし込みも見事で、多くの広告人が本キャンペーンに関して論じていた。
それからというもの、企業が行う社会的活動に関する解像度が一段上がり、「なぜこの企業やブランドが、このような活動を行うのか」が明確になってきた印象がある。まさに、乱立期から洗練期に移行する分岐点となる広告だったと言えるだろう。
▶Like a Girl
売上向上を後押しする社会活動へ
洗練期に入りしばらくすると、「なぜこの企業やブランドが、このような活動を行うのか」という一対一対応が、自社の売上向上にも貢献する、という理解が深まってきた。それまで、社会的活動は企業が公共の器として果たす役割のひとつで、コストである、という考え方が一般的であった。さらに言えば、社会的活動と売上を結びつけることは、ある種、タブー視されてきた。
しかし、18年のカンヌライオンズ講演において、価値のある報告がされた。世界的な消費財メーカーであるユニリーバが主催するセッションで、CMOケイス・ウィード氏は、「持続可能な活動を行っているブランドは、ほかの事業と比較して、約50%早いスピードで成長している」と報告したのである。加えて、「(持続可能な社会への貢献という)目的のある、成長を得ることができれば、本当にビジネスに影響を与える」とも発言しており新たな広告と社会的活動との関係を示唆する分岐点となった。
こうした事実に基づいた前向きな発言によって、メーカーや広告業界のソーシャル・グッドやSDGsに対する意識を一気に更新できるのも、カンヌライオンズの良いところであろう。これからは、社会活動のための社会活動はなくなり、自社の発展と社会の発展が両立する、本当の意味での持続可能な活動が生まれてくることになることが期待する。
いま改めて考える、カンヌライオンズから広告が抜けた意味
カンヌライオンズの歴史の中で、11年から〝広告〟の文字が抜けたことは、大きな変化であろう。当時は「PRやデザインの部門を新設するなど、年々カテゴリーを増やす中で、広告の祭典とする従来の定義が適切でなくなった」という背景があった。
しかし、いま振り返ってみると、「社会は広く告げるだけでは何も変わらず、具体的な取り組みによってのみ前進し得る」という考えの下に、多くの民間企業が社会が内包する課題を解決すべく活動を生み出し始めたからと言ったほうが合点がいく。
新しいカンヌライオンズの受賞作品が生まれない今年、大きな潮流を捉えながら、今後自分たちがどのような広告を制作していくべきかを、腰を据えて考える機会にしてはいかがだろうか。


