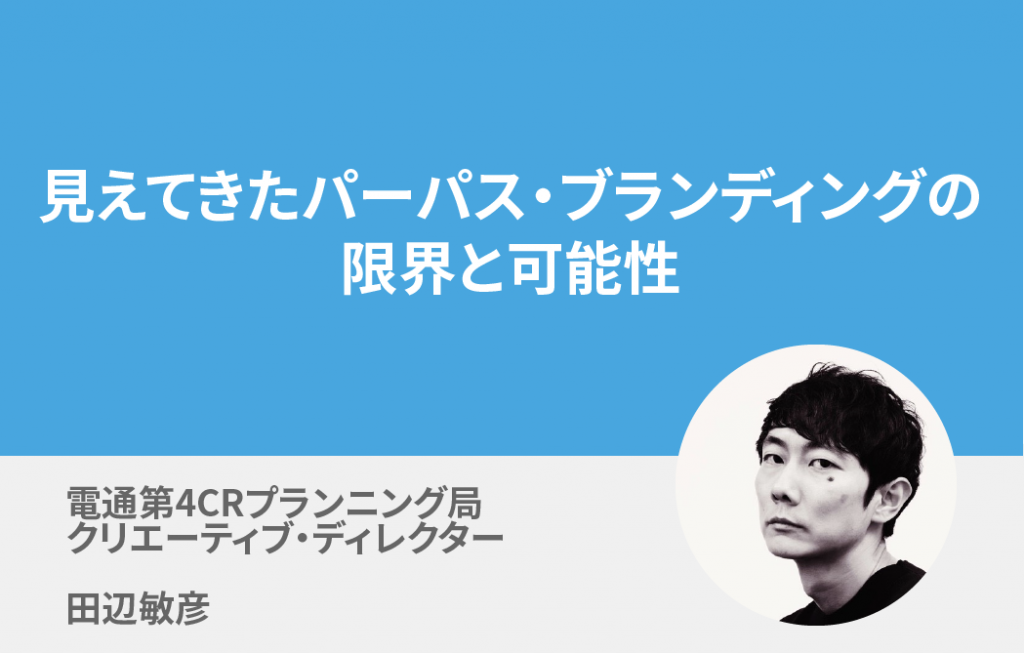
2020年は、私たちの日常が、脆い薄氷の上に成り立っていることを教えてくれた。未知のウイルスにより全人類の3分の1は自宅待機を強いられ、黒人男性への暴力行為を記録した1本の動画が、世界的な人種差別撤廃運動に火をつけた。社会が大きな転換点を迎える今こそ、企業広告の変化について考えたい。広告は、これまで以上に鮮明に、社会を映す鏡になることを求められるのだから。
私も審査員を務めた19年のカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルでは、21個のグランプリの内、実に16個が社会課題に取り組むキャンペーンに授与された。「ESGと広告」というテーマで相談を受ける機会も増えた。あえて言わせてもらうと、ここに大きな誤解がある。まず「企業が社会課題とどう関わるか」は広告という狭い枠の中で考えるべきものではなく、経営の根幹と照らして考えるべき課題だからだ。新型コロナウイルス禍と人種差別問題という、世界を巻き込む2つの社会課題のレンズを通して、パーパス・ブランディングの本質について考えてみたい。
発信したい企業と、うんざりする人々
まだ世界中の都市がロックダウンされていた20年4月、1本の動画が欧米の広告関係者の間で話題になった。“Every Covid-19 Commercial is Exactly the Same”(コロナ関連のCMはどれもまったく一緒だ)というタイトルの動画は、大半の企業のコロナ期のCMが、あるテンプレートに陥っていることへの皮肉だ。耳障りのいいナレーション、憂いをたたえたピアノ。ロゴをすげ替えればどこの企業でも成立する。ここにブランドたちのジレンマが端的に表れている。目前の社会問題に対して沈黙すれば無関心と非難され、大胆すぎるメッセージで炎上するのも怖い。その結果、無害な社会的メッセージ広告が量産されていった。エシカル(倫理的な)購買行動を意識し、多くの企業が発信を始めたが、消費者の目も以前よりシビアになっている。20年、生活者はかつてなく大量の「企業の社会的メッセージ」を浴びることになり、ある種の飽和状態が生まれた。要するに、みんな企業の綺麗事に少しうんざりしてきているのだ。
この6月、世界で最もシェアされたSNS投稿の1つはNIKEの「For once, Donʼt Do It.」だろう。かの有名な「Just Do It.」を「Donʼt Do It.」に変えたことで、人種差別問題に対するNIKEの本気度を表現した。完璧に計算されたコピーワークである。世界一洗練されたパーパス・ブランディングを行うNIKEとワイデン&ケネディによるこの投稿は業界の内外で賞賛を集め、まるで19年のカンヌでグランプリに輝いた「Dream Crazy」の再現かのようだった。NIKEを追いかけるように、ネットフリックスなどアメリカを代表するプラットフォーマーたちが続き、瞬く間に数百社が#BlackLivesMatterへの賛同を表明した。しかし、投稿から数日。世間の反応は決して賞賛一辺倒ではなくなっていた。
NIKEのインスタグラムの投稿には540万「いいね」がついている( 20年6月10日現在)。しかし、コメント欄には「メッセージではなく具体的な支援」を望む声も多い。「SAY」だけではなく「DO」を求める声だ。
これはNIKEに限った現象ではない。黒人差別問題に対して沈黙しているとの批判を恐れて、多くのブランドが賛同を表明したが、「指一本でできるSNS投稿で済ませるのか」という批判の声も聞こえる。逆に、行動に移したブランドは高い評価を獲得した。
LEGO社は、黒人への警察権力の乱用に対して抗議するだけではなく、自社商品の中で警察を扱う商品のすべてのマーケティングを中止することを宣言。子どもたちに人種の平等を教えるためとして、非営利団体に400万㌦(約4億円)の寄付も同時に行ったことで話題を呼んだ。
NIKEの投稿から数日後、ワシントンポストがNIKEの役員が白人ばかりであることを公表し、大企業の自己欺瞞を批判して話題となった。エスティ・ローダーは「黒人コミュニティと共に歩む」と投稿したが、その直後に自社の従業員100名から経営の実態が伴っていないと非難され、インクルーシブ(包摂的)な経営方針に転換することを慌てて発表することとなった。
これは今回の人種差別問題に限った話ではない。環境問題でもジェンダーでも同じである。発言に実態が伴っていないと、「自社の不都合な真実」を指摘されることになる。「賛同」ではなく「行動」を評価する流れは、広告賞においても強まっている。グランプリ作品と同じテーマに取り組みながら受賞を逃すエントリーの多くは、「呼びかけ」で終わっており「解決」に向けたアクションまで提示できていない。今後はますます言動ではなく行動で示すことが、パーパス・ブランディングの成功の与件となるだろう。
ESGをただのアリバイと考えるか成長戦略の核心に据えるか
環境負荷を低減したサプライチェーンの構築や、ジェンダーバランスに配慮した雇用計画の実現は素晴らしい。でも、それらは企業評価にケチをつけられないための必要条件であり、もはや十分条件とは言えない。ESGをブランドの成長ドライバーとするためには、明快な選択と集中が必要だ。SDGsだけでも17の領域がある。そのすべてに本気で取り組む企業があったとしたら、きっと1年で潰れるだろう。企業は慈善団体でも国連でもないのだから。本業と密接に関わる領域を選び、同業他社が真似できないくらい本気で取り組む。それがESGをブランドの価値に転換するための唯一の道である。
あえて2つの極端な事例を紹介しよう。Everlaneというアパレルブランドがある。「透明性」はもはや21世紀の企業の合言葉だが、Everlaneが掲げるのは「Radical Transparency=徹底した透明性」だ。一つひとつの材料に到るまで原価開示し、自社工場の従業員の稼働時間など、すべての企業活動を公開。「正しい消費」にこだわるミレニアルズを中心に、支持と利益を伸ばしている。彼らにとって過剰なまでエシカルであることは、株主へのアリバイではなく、成長戦略と差別化戦略の根幹なのだ。
もう1つ事例を。歌手のリアーナが立ち上げたFenty BeautyというコスメブランドとSavage X Fentyというランジェリーブランドは、徹底的に美しさのステレオタイプを否定することで差別化している。Savage X Fentyのインスタグラムを見れば、1秒で違いに気つくはずだ。モデルではなく、多様な体型の女性たちが起用され、商品開発も徹底的にインクルーシブなブランドの姿勢に基づいている。ランジェリー業界のかつての覇者であるVictoriaʼs Secretは、古い女性のステレオタイプを押し付けた結果、正式にブランドの売却が決まった。
広告だけがESGを意識しても意味はない
繰り返しになるが、広告の小手先だけESGを意識しても企業価値は生まれない。今の日本は、企業が社会課題を扱うだけで拍手される、いわば初期のボーナスステージにいる。
でもこの状況はいつまでも続かない。エシカルなブランド選択を行う若い世代が購買力を増し、SNS上での社会的な発言を恐れない人々も増えるだろう。グローバル市場を狙うブランドであれば、ESGを経営に組み込むことはもはや規定演技である。その時に広告の表面をESGでお化粧しただけのブランドは無視されるか、すぐにメッキを剥がされることになる。大切なのは、未来のビジネスプランの中心にESGの発想をネイティブに組み込み、「実態が伴った」ブランディングを実践できるように準備することだ。未来に備えるなら、社会が大きく変わろうとしている、今だと思う。
