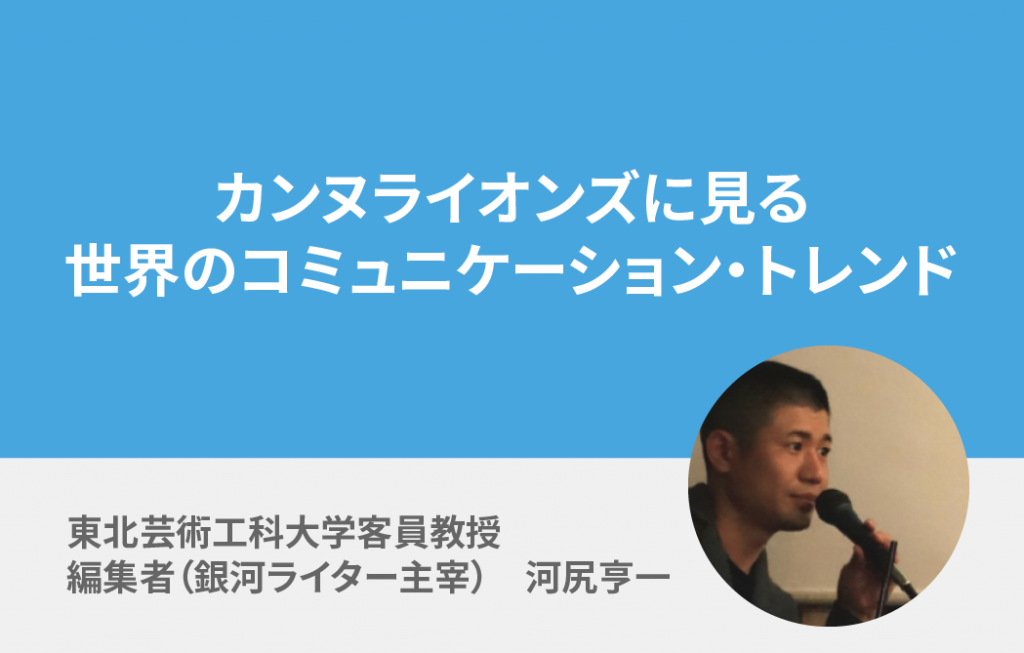
1974年大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。美大予備校講師、雑誌『広告批評』を経て、現在は実験型の編集レーベル「銀河ライター」を主宰、企業コンテンツの企画制作などを行う。翻訳書に『CREATIVE SUPERPOWERS』(左右社)等。石岡瑛子の評伝『TIMELESS』刊行予定。
筆者は、2007年より12年間「カンヌ国際クリエイティビティ・フェスティバル」(カンヌライオンズ)を現地取材してきた。ご存知のように、カンヌライオンズは世界最大級の広告クリエイティブ・フェスティバルである。毎年3万~4万ものキャンペーンやプロジェクト事例が集まるこのビッグイベントを定点観測していると、世界のコミュニケーション・トレンドが見えてくる。
19年の同フェスティバルにおいて、セミナーの登壇者や各部門の審査員長によるプレス・カンファレンスで、最も力点を置いて語られていたのは「パーパス(Purpose)」という考え方だ。このキーワードについては、本誌でも前号で特集されていたが、本稿において筆者はジャーナリストの立場から、「パーパス時代の広告」を考えてみたい。
まず明らかにしておきたいのは、「パーパスとは一体何を指すのか?」という問題だ。これはわかるようでわからない言葉である。カンヌ現地においても、人によりその意図するものが異なるため、明確な定義は難しい。
だが、おおよその共通見解は存在する。本稿では「ブランドの〝社会的〟存在目的」という定義でパーパスを捉えたい。より平たく言うなら、企業キャンペーンやプロジェクトに、「様々な社会課題を解決するアイデアやアクションが含まれていること」が、パーパスのある施策ということになる。ここで言う社会課題は多岐にわたるが、主にはジェンダー・イコーリティー、障がい者支援、地球環境、人種差別、貧困・格差、紛争、教育、銃問題、政治腐敗などだ。
カンヌを席巻するパーパス施策
近年のカンヌライオンズでは、パーパスのある施策が高く評価される傾向が強い。19年の受賞結果を見ても、元NFL選手でいまは社会活動家のコリン・キャパニックほか、世の中に〝物申す〟アスリートたちを起用したナイキ「ドリーム・クレイジー」手足が不自由な子どもたちもゲームを楽しめるアダプティブ・コントローラーを開発し、それをスーパーボウルのCM枠で大々的にアピールしたXbox「ウィ・オール・ウィン」などが、グランプリや複数部門でのゴールドを受賞。1年を代表するキャンペーンとして喝采を浴びていた。
プロジェクト型の施策では、その傾向はさらに顕著だ。例えばPR部門でグランプリを受賞した「タンポン・ブック」(フィメール・カンパニー/ドイツ)。女性用生理用品を贅沢品と見なして高率の付加価値税(19%)をかけるのは性差別だとして、タンポンを書籍の〝おまけ〟にすることで低税率(7%)で販売、それにより話題づくりをしながら法改正の署名運動を行う施策である。このプロジェクトを契機とする署名運動の盛り上がりを受け、ドイツ議会は20年からタンポンの税率を引き下げる法改正を行った。まさに広告が社会を変えた事例だろう。
ここに挙げたのは、19年にカンヌで受賞したパーパス型施策のごく一部だ。活字では現地の「空気」まで伝えることが難しいのだが、現在はこういったトレンドがフェスティバルを席巻していると言っても過言ではない。会期中に100回以上開催される公式セミナーでも「パーパス」は議題の中心であり、ある意味では「テクノロジー(AIやイノベーション)」以上に注目を集めるテーマになっている。19年にユニリーバが主催したセミナーでは、CEOのアラン・ヨーペ氏が次のようなコメントをしていたのが印象的だった。
「パーパスの時代にはとても刺激的なチャンスがある。ものごとを適切に責任を持って行うことで、マーケティング業界に対する信頼を回復し、優れたクリエイティビティを解き放ち、愛するブランドを成長させることができるからだ。社会的課題意識を持たない広告(ウォーク・ワッシング)は、ブランドのパーパスを汚染し、我々の産業を衰退へと向かわせるだろう。パーパスのあるブランドのコミュニケーションは、単に人々を叫ばせ、ものを買わせるだけのものではない。いまの世界に対してアクションを起こすものである」
このコメントから抽出できるポイントは2点。1つは、現代のグローバル企業は、パーパスを前世紀的な意味での〝社会貢献〟施策と捉えていない、ということ。つまり慈善やチャリティではない。彼らはそれが「ブランドの成長を牽引する」という確信のもとに動いている。事実、ユニリーバ社のプレス向けの動画では、同社のパーパス型の施策を展開する28ブランドが、そうでない同社ブランドと比較して69%スピーディに成長し、グローバルでの成長全体の75%を担っているとリポートしている。
ポイントのもう1点は、「ウォーク・ワッシング」への警戒心だ。社会的課題意識を持たず、商品名やキャッチフレーズをやみくもに連呼し、ときには表現の中で差別的マインドまで露呈させているコミュニケーションは、炎上騒動を起こして社会に煙たがられるだけで、ブランドの成長を促進することもなく、業界全体の価値を棄損するとヨーペ氏は警告している。「Goods(商品の訴求)」から「Good(社会課題の解決)」へとシフトする21世紀広告のマインドをこの発言から読み取ることもできるだろう。
グッドからパーパスへ
その上で、1つ補足しておきたい。本稿で筆者が「パーパス化」というキーワードで語っている現在の動きは、ここ数年で顕在化したものではない。09年のカンヌライオンズで最高評価を受けた「オバマの大統領選挙SNSキャンペーン」をはじめ、その萌芽は遅くとも10年前には現れており、その後ムーブメントが拡大、10年代後半になって広告戦略として定着した。10年代前半は「ソーシャル・グッド」あるいは単に「グッド」と、どちらかと言えば社会貢献性の強いものとして捉えていた概念が、毎年の議論の深化を経て、「パーパス」の言葉で実践的メソッドとして語られるようになっている。この10年間に及ぶ、ポスト・リーマンショックの膨大な取り組みの集大成として編み出されたのが「パーパス理論」であることは押さえておきたい。
ある意味でパーパスは、テクノロジー化の波に押され、世界的に影響力を低下させているマーケティング産業が、次の時代をサバイブするための知恵とも言える。「もはやパーパス型のブランディングしか方策がない」というのが、世界の本音なのかもしれない。いずれにせよ、パーパスと呼ばれる一連の現象は、トレンドといった一過性のものではなく、「21世紀広告の理想的フォーマット」として提示されたソリューションであることに留意すべきだ。カンヌは世界の先進的施策の中から、未来の広告の行き先を探る巨大な実験場でもある。
パーパス化は広告産業だけでなく、いまの世界全体の潮流でもある。現代のティーンエイジャーたちは、ロジックではなく時代のフィーリングとして、パーパスの空気を自然に呼吸しているようだ。例えば筆者が最近、コミュニケーションのスタイルに関して、極めて現代的だと感じるのは、グレタ・トゥーンベリの振る舞いである。
10代の環境活動家として船や鉄道、あるいはEV(電気自動車)で世界を飛び回るグレタは、「①社会課題の解決をテーマに掲げる」「②大胆なアクションによって賛否両論を巻き起こしバズを生む」といった、パーパス時代のコミュニケーションを自然体で実行している。さらに寄付や書籍販売など「③〝ビジネス〟は好調」で、便乗商法を防ぐべく彼女は自身の名を商標登録しているほどだ(環境活動を行う財団も設立)。好き・嫌いは別として、グレタを〝現代広告〟の成功例として眺めると、カンヌライオンズのパーパス化も理解しやすいだろう。逆にカンヌを長年ウオッチしていると、いま、なぜグレタがブレイクするかも実感としてよくわかる。彼女はパーパス時代のアイドル(偶像)なのだ。
コロナショック後の世界では、パーパス化の傾向がさらに顕著になるのではないだろうか?
